ソーシャルレンディングの確定申告のやり方!必要となるケースや書類の書き方も解説【決定版】
ソーシャルレンディングを利用する際、気をつけておきたいのが確定申告です。確定申告をしっかりとしないと、脱税になってしまうおそれがあります。本記事では、ソーシャルレンディングの利用で確定申告が必要な場合や手続きのやり方を解説します。

ソーシャルレンディングに確定申告は必要?
投資家個人がソーシャルレンディングによって利益を得た場合、確定申告が必要となります。本章では、ソーシャルレンディング利用時の確定申告について解説します。
ソーシャルレンディングとは
ソーシャルレンディングは、資金を運用したい人々と資金が必要な事業者をオンラインでつなげる投資サービスです。特に、資金調達を求めるベンチャーやスタートアップ企業に人気です。
投資家はソーシャルレンディングのプラットフォームと匿名組合契約を結び、出資した資金が事業者によって運用されます。投資は少額から可能で、興味のあるさまざまなプロジェクトに分散投資できる点が魅力です。プラットフォームは、多くの投資家から集めた資金を組み合わせ、それを資金ニーズのある事業者へ融資する役割を担います。
確定申告が必要な場合
ソーシャルレンディング利用で確定申告が必要な場合を3つのケースに分けて解説します。
会社員の場合
ソーシャルレンディングは源泉徴収されるため、確定申告が要らない人も多いです。例えば、会社員ならば確定申告が不要なことも。基本的にサラリーマンであり、雑所得が年間20万円以内であれば確定申告は不要になります。
しかし、給与所得が2000万円以上あったり、雑所得20万以上あったりする場合には確定申告が必要です。他に、ソーシャルレンディングとは直接的には関係ありませんが、2箇所から給与を受け取っている、給与所得や雑所得以外の所得が20万円以上ある人等も確定申告が必要です。
ちなみに、ソーシャルレンディングはマイナンバーと紐付けられており、脱税すると必ずバレる仕組みになっています。もしも確定申告する必要性がある場合には必ずしておきましょう。
個人事業主やフリーランスの場合
サラリーマンと違って個人事業主やフリーランスの場合、基本的に確定申告はする必要性があります。全く所得を得ていないのであれば別ですが、そうでない場合には基本的に個人事業主やフリーランスは確定申告が必要になってきます。
専業主婦の場合
専業主婦の場合でもパートで給料を得ていることがあるでしょう。この場合、基本的に会社員と同じように年末調整されている場合には確定申告は不要になります。しかし、専業主婦の場合には所得額の合計が38万円を超える場合には確定申告が必要となってきます。例えば、ソーシャルレンディングだけでなくパートや、内職をしていて、所得額が38万円を超えたら確定申告しておきましょう。
また、アルバイトやパートは必要以上に源泉徴収されていることも多くなっています。もしも年末調整されない職場ならば必ず自分で確定申告をしておくべきでしょう。ソーシャルレンディング等の分配金から源泉徴収された金額が還ってくることもありますので、申告しておくべきです。
確定申告が不要な4つの場合
- 給与の支払を一か所からのみ受けており 年収が2000万円以下で ソーシャルレンディングとその他の所得の合計が20万円以下の場合
- 給与の支払を二か所からのみ受けており 年収が2000万円以下で年末調整をされていない給与の収入金額とソーシャルレンディングとその他の所得の合計が20万円以下の場合
- 公的年金の収入金額が400万円以下で それ以外の給与およびソーシャルレンディングとその他の所得の合計が20万円以下の場合
- 給与および公的年金 ソーシャルレンディングなどその他の所得の額が 基礎控除や社会保険料控除などの控除額合計以下の場合
ソーシャルレンディングをしていても確定申告が不要になることがあります。例えば、経費が嵩んで雑所得が0円以下になる場合にはもちろん確定申告は不要です。他にも、給与の支払いを一箇所からのみ受けており、年間の雑所得の合計額が20万円以下の場合にも確定申告は不要になります。
また、給与の支払を複数から受けており年末調整をされていないといった場合や、給与の収入金額とその他の所得の合計が20万円以下の場合、給与やソーシャルレンディングなどその他の所得額の合計が基礎控除等の控除額の合計以下になる場合にも確定申告は不要です。この場合でも確定申告をしておけば還付が受けられることもあるので、確定申告をしておいて損はありません。
非公開: 2024年の確定申告の期限はいつまで?変更点や注意点も徹底チェック!
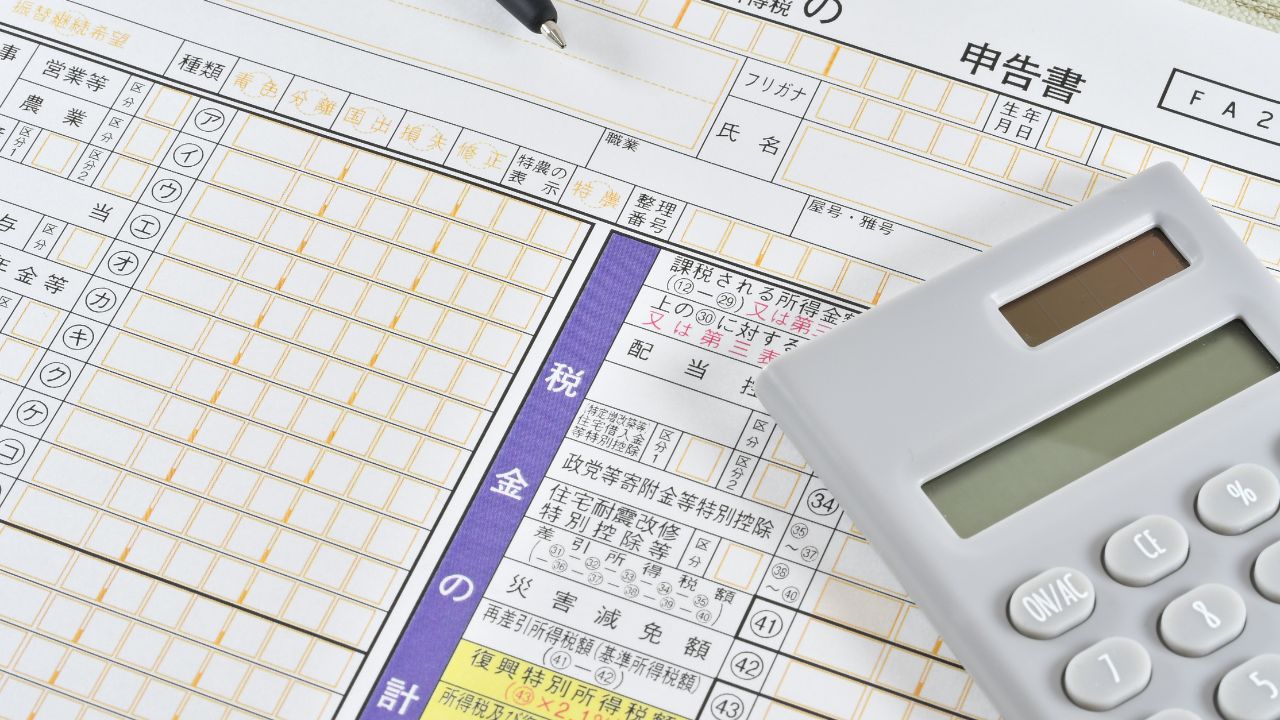
この記事では、2024年の確定申告の提出期限や納税期限を解説しました。2023年の確定申告からの変更点や必要書類、申告書の提出方法を紹介しています。インボイス制度へ登録した方に向けて消費税の申告期限も説明したので、ぜひ記事を読んでください。
確定申告が不要でも住民税の申告は必要
確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。住民税の申告をしなかった場合のリスクや、申告方法を順番に解説します。
住民税の申告をしなかった場合
ソーシャルレンディングの雑所得が年間20万円以下であれば確定申告は不要になります。しかし、サラリーマンであっても住民税の申告は税務署または地方自治体にする必要性があります。個人事業主の場合には特に確定申告だけでなく住民税の申告もしないと、健康保険料等の費用も確定しません。
また、住民税には所得割と均等割の区別があり、それぞれで課税条件も変わってきます。市町村によって利用できる控除も多々あるだけでなく、税率も千差万別です。このため、実際にいくら納めるべきかはじっくりと市町村のホームページを見て確認しておいて下さい。
もしも住民税の申告が必要なのにしないと延滞金等がかかってきます。他に、市町村から目をつけられて、次年度からお尋ねが着やすくなることも。他に、市民サービスの利用が制限されてしまうということもあります。ソーシャルレンディングで儲けたお金を散財してしまって納税できないということもありますが、この場合にも申告だけはして納税は延期してもらうようにシましょう。
こうしたこともあるので、「確定申告が不要だから住民税の申告も要らないはず」と気軽に考えずに、しっかりと市町村のページを見て確認シておきましょう。
住民税の申告方法
確定申告が不要な場合であっても住民税の申告が仏様な場合、実際にはどのようにすればよいのでしょうか。こうした方法は市町村によっても微妙に異なるのですが、基本的なやり方はほぼ同じです。まず、市町村のホームページを確認して住民税申告に関する情報を確認して下さい。電話で問い合わせても問題ありません。ここにその市町村毎の税額や申請・納税方法等が記載されています。
市町村によってはホームページで簡単に納税額のシミュレーションが出来るといったところもあります。申請書もホームページから基本的にダウンロード可能です。
次に必要な書類を集めましょう。必要となるのはダウンロードした住民税申告書、印鑑、身分証明書、源泉徴収票、控除証明書、終始内訳書等です。細部は市町村によって異なってきます。此等を集めて郵送で提出しましょう。もしも不安ならば直接窓口に行って書類が整っているか確認することもお薦めです。
ちなみに申告はネット申告することも可能です。東京の市町村は多くがネット申告することが出来るようになっています。ネット申告することで、青色申告のようにお得に控除が受けられるといったこともあるので活用してみるのもありです。
確定申告と住民税の申告は違う?計算方法や支払い方法を解説
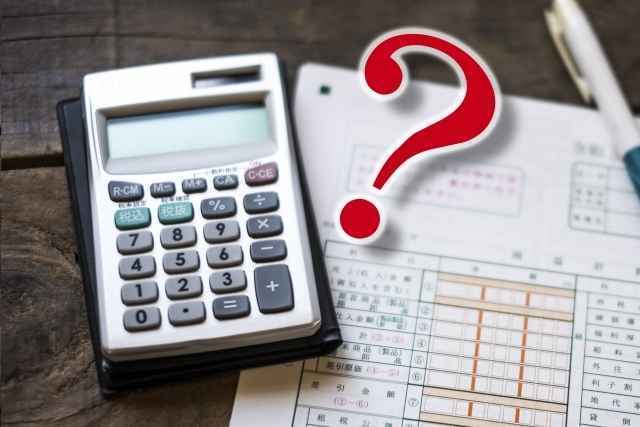
詳細はこちら
ソーシャルレンディングで確定申告をしたほうがいい場合
ソーシャルレンディングで確定申告をしたほうがいいのは、以下の場合です。
給与所得と分配金の合計が195万円以下の場合
確定申告をすれば還付金を貰えることがあります。そもそもソーシャルレンディングで得られる配当金は既に20.42%の源泉徴収がされています。ですが、源泉徴収額は所得税とは限らないのです。源泉徴収はあくまで予想される所得税を事前に差し引いているだけであり、実際の所得税額とは異なることがあります。
例えば、本業で赤字を出すと、所得税が20.4%よりも低くなることがあります。他に低所得者だと所得税額も低いですから、この場合にも還付申告をすることで還付される可能性があるのです。 実際の収めるべき所得税額を知るためにも、やはり一度確定申告をして計算してみることが大事。
確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、しっかりと計算することで還付が受けられることが判明することも。また、実際には納税が必要なことがわかるといったこともあります。 こうした計算も簡単に国税庁のホームページで可能です。もちろん税理士に相談することも可能。
ソーシャルレンディングの利益に対する課税の仕組み
ここでは、ソーシャルレンディングの利益に対する課税の仕組みをわかりやすく解説します。
ソーシャルレンディングの分配金は雑所得
まず、ソーシャルレンディングをして得た配当金は雑所得として扱われます。給与所得や配当所得で計上して間違える人が多いですから、気をつけて下さい。配当金からソーシャルレンディングをするのにかかった経費を除き、雑所得で計算します。経費としては通信費用やセミナー代金、交通費用等を計上することが出来ます。経費には認められないものもあるので注意が必要。
一方、ソーシャルレンディングを利用する際に色々とキャンペーン金などが得られることがあります。こうしたキャンペーンや募集斡旋で貰った金銭は、一時所得で扱われます。一時所得の場合、50万円未満であれば全額免除、それ以上であれば50万円免除になるという特例があります。
ソーシャルレンディングは総合課税

ソーシャルレンディングは総合課税です。つまり、給与所得等と合算してその合計額に対して課税されることとなります。これは他の投資方法とは大きく異なる点でしょう。例えば、FXであれば分離課税が基本になっています。総合課税のほうがお得に納税出来ることが多いですから、これはソーシャルレンディングの利点といっても良いかもしれません。
合算されますから、実際の課税額は給与所得等によっても大きく変わってきます。給与所得が多ければ多いだけ納税額も当然累進的に高くなってきます。また、所得が少ない場合には納税が不要になるばかりか、確定申告をすることで還付を受けられるといったこともありますから、やはり確定申告はしておくべきです。
ソーシャルレンディングの分配金は源泉徴収されている
ソーシャルレンディングをして得た配当金や分配金は既に源泉徴収されています。つまり、業者が配当金から想定される所得税分を差し引き、その差し引かれた配当金を利用者に渡しています。納税は代わりにやってくれるので便利なものの、逆に所得税を払い過ぎていることもあります。この場合には確定申告をして還付申告をする必要性があります。
実際に源泉徴収されている税額は20.42%です。内訳は所得税が20%、復興特別所得税が0.42%となります。復興特別所得税は2037年まで継続予定です。このように、配当金にかかる税金はかなり高めになっていることもあり、後述するように、色々と工夫をシて節税をしていかないといけません。
住民税については源泉徴収が行われていない
ソーシャルレンディングからの分配金にかかる税金では、所得税(復興特別所得税を含む)は源泉徴収されますが、住民税はその場で徴収されない仕組みになっています。確定申告を行う場合、住民税に関する追加の申告は不要です。
しかし、確定申告を行わない人は、住民税が正確に計算されるよう、住民税の申告を別途行う必要があります。
ソーシャルレンディングの確定申告のやり方
本章では、ソーシャルレンディング利用による確定申告のやり方を紹介します。
必要書類の確認
確定申告をする際に必要な主な書類は、確定申告書の第一表と第二表です。また、確定申告書を作成する上で、ソーシャルレンディングからの分配金額や源泉徴収税額を示す書類(例えば年間取引報告書)が必要になりますが、これらは提出書類ではありません。
確定申告時には、マイナンバーの提示が必要であり、提出方法によっては身分証明書のコピーなど、本人確認書類の提出が求められる場合もあります。
確定申告書の書き方
ソーシャルレンディングから得た分配金の確定申告方法について簡潔に説明します。
まず、ソーシャルレンディングからの年間取引報告書を準備します。この報告書に基づき、確定申告書第二表の「所得の内訳」欄に必要情報を記入します。分配金は「雑所得」として扱われるため、「所得の種類」には「雑所得」、「種目」には「分配金」と記入します。支払者の名前や住所欄には、ソーシャルレンディング事業者の情報を入力します。収入金額欄には、受け取った分配金の額を、源泉徴収税額欄には源泉徴収された税金の額を記入します。
収入の合計を収入金額欄に、そして経費がある場合は、収入から経費を差し引いた額を所得金額に記入します。この例では、ソーシャルレンディングの分配金に関連する経費は発生していないと仮定しています。もし他に雑所得があれば、それらを合わせて計算します。
最後に、源泉徴収された税金額を確定申告書の「税金の計算」欄に記入します。これで、所得税の計算時に源泉徴収された税額が適切に考慮されます。
確定申告書等作成コーナーにおける申告フロー
確定申告書をオンラインで作成する大まかな手順を説明します。
最初に、「確定申告書等作成コーナー」のウェブサイトにアクセスし、「作成開始」をクリックして始めます。その後、提出方法を選ぶ画面が出てきますので、希望する提出方法を選んでください。電子申告を希望し、マイナンバーカードを持っている場合は、スマートフォンまたはICカードリーダーを使ったe-Taxのオプションを選びます。マイナンバーカードがない場合は、IDとパスワードでのe-Taxが適切です。紙での提出を希望する場合は、書類を印刷して提出するオプションを選んでください。
次に、所得税の申告を選択し、「作成開始」ボタンをクリックします。申告者の生年月日を入力し、ソーシャルレンディングからの分配金を含む所得についての質問に答えます。ソーシャルレンディングの収入は雑所得に該当するため、収入の質問で「はい」と回答します。
この後、確定申告書の具体的な入力画面に移ります。ソーシャルレンディングの分配金を雑所得の欄に記入します。「雑(その他)所得」の入力画面で詳細を入力し、確認画面で入力内容を確認します。
最後に、収入、所得、源泉徴収税額など、必要な情報を正確に入力し、所得控除やその他必要な情報を追加していきます。これで、オンラインでの確定申告書の作成と提出が完了します。
ソーシャルレンディングで節税をする方法
ここでは、ソーシャルレンディングで節税をする方法を簡単に解説します。
経費を計上する
- 振込手数料
- セミナーの参加費や交通費
- ソーシャルレンディング関連の書籍代
- インターネットの利用料
ソーシャルレンディングでよりお得に確定申告するコツの一つが経費の活用です。経費としてはソーシャルレンディングについて学ぶために必要なセミナー代金や書籍代金、情報集めに必要な通信費用、納税に当たって助言を受けた場合には税理士費用等が計上できます。場合によっては電気代や家賃も一部形状可能ですが、やり過ぎると税務署からお尋ねされます。
家族の収入が低い方の名義で投資をしてもらう
ソーシャルレンディングを妻等にしてもらうのもありです。つまり、仕事をしていない人にもーシャルレンディングをしてもらえば、節税できることがあります。例えば、ソーシャルレンディングで100万円を投資して年間に30万円儲けられる可能性がありそうだとしましょう。この場合、夫が50万円分、妻が50万円分をそれぞれ投資すれば、夫は年間に15万円、妻も年間15万円にソーシャルレンディングによる所得額を抑えることが出来ます。
これにより所得額を収めなくてよくなるだけでなく、所得額の確定申告も不要になります。もちろん、計画通りに行かなくて儲かりすぎた場合にはしっかりと申告もする必要性があります。この分散法は家族が多ければ多いだけ活用しやすいです。
法人をつくる
ソーシャルレンディングでまとまった収入が得られるようになったら、法人化してみるのもありでしょう。会社員の場合には気軽に出来ませんが、個人事業主等ならば是非ともやってみる価値はあります。法人化することによって収めるべき税金が法人税になり、色々な項目を経費として計上することが可能になって来ます。また、法人になっておけば赤字の場合等には繰越等もしやすくなっていますし、色々と税的な優遇措置も多くなっています。
ふるさと納税をする
ソーシャルレンディングの案件によっては元手が数倍に増えるようなものもあります。ソーシャルレンディングの場合、2割も税金として引かれますから、かなり負担が思いです。こうした際に節税するためにもふるさと納税を活用するのもありです。ふるさと納税を使うことによって、よりお得に納税することが出来るだけでなく、特産品も貰うことが出来ます。しかし、ふるさと納税出来る学には上限もありますから、気をつけておきましょう。
ソーシャルレンディングで節税する注意点
ソーシャルレンディングで節税する注意点を2つ紹介します。
所得の損益通算ができない
ソーシャルレンディングの注意点の一つが損益通算が出来ない点です。つまり、個人事業主をしていて本業で赤字所得になった場合に、それとソーシャルレンディングで得た所得を合算して節税することは出来ません。例えば、200万円の事業所得を出し、ソーシャルレンディングで200万円の所得を得たとしましょう。
損益通算が出来れば単純にこの場合では所得額が0円になりますが、損益通算が出来ないので、ソーシャルレンディング分の納税はシないといけません。
総合課税の場合は繰越控除ができない
ソーシャルレンディングの注意点の一つが、繰越控除が出来ないということです。もしも損失を出してしまっても繰越をしたりして控除を受けたりといったことができません。繰越控除を受けたい場合には法人化するといったような方法も考えられます。
ソーシャルレンディングはリターンが大きい代わりに大損失することもありますから、繰越控除が利用できないのは大きな欠点といっても良いかもしれません。ちなみに、fx等は繰越控除が可能です。
ソーシャルレンディングの確定申告まとめ
この記事ではソーシャルレンディングに関わる確定申告について詳しく紹介シました。ソーシャルレンディングで儲けた際にはしっかりと確定申告をしないと脱税になることがあるので、しっかりと気をつけておきましょう。
また、ソーシャルレンディングで納税する必要がある場合にも、経費をうまく使ったり、法人化したりしてよりお得に納税するようにしておいて下さい。特に経費は色々なものが挙げられることから色々と計上して少しでも負担を減らしていくべきです。
他にも盲点になりやすいのが住民税の申告です。これをしていなくて市町村からお尋ねが来るといったこともありますから、問題にならないように確実に申告もしておきましょう。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。

 お問い合わせ
お問い合わせ
 税理士紹介の無料相談はこちら
税理士紹介の無料相談はこちら











