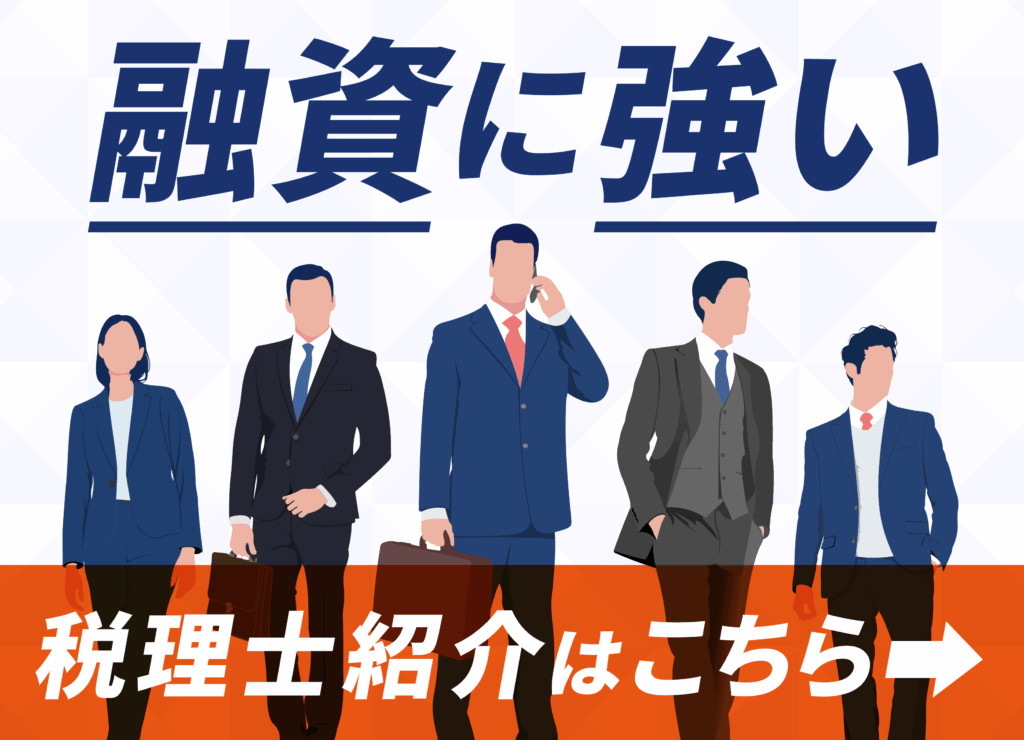確定申告の期間はいつまで?提出方法から納付期限を過ぎた場合の対処法も解説!
この記事では、確定申告書の提出期間と納税期間を解説しました。e-Taxや郵送を使った確定申告書の提出方法や、事前に用意する必要書類を詳しく紹介しています。提出や納税期間を過ぎた場合の対処法も解説したので、ぜひ最後まで記事を読んでください。

確定申告書の提出期間や所得税の納税期間がわからずに、不安を感じている方も多いのではないでしょうか?2月〜3月にかけては消費税の納税期間や贈与税の納税期間も重なるので、支払い管理はとても重要になります。
そこで本記事では、確定申告書の提出期間や納税期間を詳しく解説しました。確定申告に必要な書類や、税務署への提出方法も紹介しています。ぜひ最後まで記事を読み、期間内に申告を済ませてください。
確定申告の期間はいつからいつまで
確定申告書の提出と所得税の納税期間、所得税以外の税金に関する申告と納税期間を解説します。
確定申告・納税期間
確定申告書の提出と所得税の納税期間は、毎年2月16日〜3月15日までです。3月15日が土日・祝日の場合は、翌月曜日まで提出と納税期間は延長されます。
確定申告書の提出方法ごとの締切時間は、以下のとおりです。
- 税務署の窓口:3月15日の17時まで
- 時間外収受箱:3月15日の23時59分まで
- 郵送:3月15日の消印有効
- e-Taxによる電子申告:3月15日の23時59分まで
税務署に設置している時間外収受箱やe-Taxを活用すると、窓口で提出するよりも締切時間を伸ばせます。
所得税以外の税金に関する申告・納税期間
消費税と贈与税の申告と納税期間を解説します。
消費税
消費税の申告と納税期間は、申告する期間の翌年1月1日〜3月31日までです。3月31日が土日・祝日の場合は、翌月曜日まで提出期間と納税期間は延長されます。
インボイス制度を機に課税事業者になった方は、必ず消費税の申告と納税を行いましょう。消費税のしくみや計算方法は、以下の記事を参考にしてください。
【個人事業主の確定申告】消費税の申告のしくみと計算方法

詳細はこちら
贈与税
贈与税の申告期間と納税期間は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日までです。贈与税の申告は、贈与を受けた人が行ってください。
所得税と消費税、贈与税それぞれで提出と納税期限は異なるので、忘れないように注意しましょう。贈与税については、以下の記事で詳しく解説しています。
非公開: 贈与税の申告は税理士に相談すべき?報酬や費用・メリット・注意点まで解説!

税理士に贈与税の相談をすれば、税額の計算はもちろん、申告手続きやどのように贈与すれば有利になるのかなどの観点からアドバイスを受けられます。この記事では、贈与税の基本情報や相談できる場所、相談・依頼した時にかかる費用、相談するメリット・注意点、税理士の選び方などを紹介します。
還付申告の申告期間
所得税や復興特別所得税、消費税などを納めすぎた場合は、還付申告をすると払いすぎた税金が手元に戻ってきます。還付申告は年間を通していつでも行え、5年間有効です。
仕事が忙しく書類の準備や申告書の作成が遅れても、5年以内なら問題なく還付申告ができます。払いすぎた税金が還付される場合は、必要書類に金融機関の口座番号を記入してください。
書類を提出してから3週間程度で、登録した口座へ還付金は振り込まれます。還付金の計算方法を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
確定申告の還付金はいつ・いくら返ってくる?計算方法や期間を解説

確定申告における還付金とは、源泉徴収や予定納税などにより既に納めた税額が実際の所得税額より大きい場合に返ってくるお金です。今回は確定申告で受け取れる還付金について、計算の仕方や受け取る方法、受け取り時期などを詳しく解説します。
確定申告に必要な書類
確定申告時に用意する書類を解説します。
必ず必要な書類
確定申告時には、以下の書類を用意してください。
- 確定申告書
- 本人確認書類
- 源泉徴収票
- 控除証明書
- 収入の書類
- 経費の書類
- インボイス登録番号
確定申告時に控除を申請すると、支払う税金を少なくできる可能性があります。控除申請に必要な控除証明書は、11月頃に自宅へ郵送されます。
控除証明書を紛失した場合は再発行ができるので、早めに申請しましょう。
確定申告書の第一表と第二表は、税務署や確定申告会場、市役所や区役所など窓口で取得するほか、国税庁のWebサイトからもダウンロード可能です。青色申告をする方は、確定申告書とあわせて青色申告決算書も以下のWebサイトからダウンロードしてください。
参考:所得税青色申告決算書
本人確認書類
確定申告時には、以下の本人確認書類が必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- 住民票の写し(マイナンバー付き)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
確定申告時には、番号確認と身分確認の書類が必要です。マイナンバーカードは1枚で両方の役割を果たすので、事前に用意すると安心でしょう。
マイナンバーカードを発行していない方は、マイナンバーの通知カードとあわせて、運転免許証やパスポートを用意してください。
申告内容に応じた書類
消費税を申告するときには、消費税及び地方消費税の申告書を用意してください。贈与税の申告では、贈与税申告書や評価明細書などの書類が必要です。
申告時に必要な書類は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
必要に応じて、以下の書類も用意しましょう。
- 預金通帳
- クレジットカードの明細
- 領収書・レシート
- 金融機関の口座番号
振替納税や還付金を受け取る場合は、金融機関の口座番号を申告書に記入してください。
確定申告の提出方法
確定申告書の提出方法を、詳しく解説します。
e-tax
e-Taxを活用すると、国税庁のWebサイトから電子申告が可能です。e-Taxで申告をするときには、マイナンバーカードとICカードリーダライタ、またはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを用意してください。
確定申告時期の税務署は混雑することが多いので、e-Taxを利用すると申告時間を短縮できるでしょう。また、青色申告で申告する場合は、e-Taxで確定申告書を提出すると65万円の控除を獲得できます。
【e-Tax】確定申告をネットで申請するやり方、必要なものを解説

確定申告=税務署に直接行って作業をするものというイメージを持っていませんか?直接提出する方法でも、税務署で書類を作成する方法と、自宅で作った書類を提出するだけの方法があります。そして直接提出する方法以外にも、複数の選択肢が用意されています。自宅で作成した書類を郵送する方法もありますが、最近ではネットから提出できる仕組みもあります。 ネットから申告する方法というのが、e-Taxを利用した方法です。パソコンやスマートフォンを活用することで、自宅にいながら申告できます。税務署まで行く必要がないので、時間がかからず、自分の好きなタイミングで申告ができるというのもポイントの1つです。提出のためにどのような準備が必要か押さえて、時間をかけずに作業ができるようにしましょう。
税務署の窓口に提出
確定申告書は、税務署の窓口でも提出可能です。税務署の窓口で提出すると、担当職員に必要書類や書類の不備などの疑問点を質問できます。
初めて確定申告をする方や申告方法に不安のある方は、必要書類を準備して開庁時間内に税務署で提出しましょう。
税務署に郵送する
確定申告書は、郵送での提出も可能です。郵送で提出する場合は、3月15日の消印まで有効となります。
確定申告書の控えが必要な方は、返信用の封筒と切手、確定申告書の控えもあわせて郵送してください。
【確定申告】確定申告書類を郵送で提出する方法と注意点

詳細はこちら
確定申告の納付期限を過ぎた場合の対処法
確定申告の納付期限が過ぎそうな場合は、延長申請や延滞制度を活用しましょう。延長申請と延滞制度を、詳しく解説します。
病気などやむを得ない事情で提出が遅れる場合
病気や災害、盗難などの被害を受けて確定申告書の提出が遅れる場合は、延長申請を税務署に提出すると申告期間が延長される可能性があります。
災害による申告、納付等の期限延長申請書には、被災状況や延長期間の日付を記入してください。
納税が期限内に間に合わない場合は延滞制度を活用
所得税の支払いが期限までに完了しない場合は、延滞制度を活用すると納税期間を延ばせます。この制度では、期限までに納税額の半分以上を支払うと、残りの金額の支払いを5月末頃まで延ばすことが可能です。
ただし、制度を活用すると利子税が発生することに注意してください。所得税の支払いが困難な場合は、制度の利用を検討しましょう。
確定申告が遅れるとどうなる?期限後申告のペナルティから対策まで徹底解説!

この記事では、確定申告の提出が遅れた場合のペナルティを解説しました。確定申告の申告期限や、期限後に提出した際に支払う税金を紹介しています。やむを得ない理由があり、確定申告を期限後に申告するときに必要な手続きも解説しました。
確定申告の期限に遅れないよう期間の確認や準備をしよう
確定申告書の提出には多くの準備が必要なので、早めに必要書類を用意して申告書を作成しましょう。所得税以外に消費税や贈与税の申告をする方は、提出と納税期間が異なるので十分注意してください。
やむを得ない理由があり確定申告書の提出や納税期間に遅れる場合は、税務署に必ず相談してください。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。

 お問い合わせ
お問い合わせ
 税理士紹介の無料相談はこちら
税理士紹介の無料相談はこちら