【最新版】贈与税とは?税率や計算方法、非課税制度も紹介
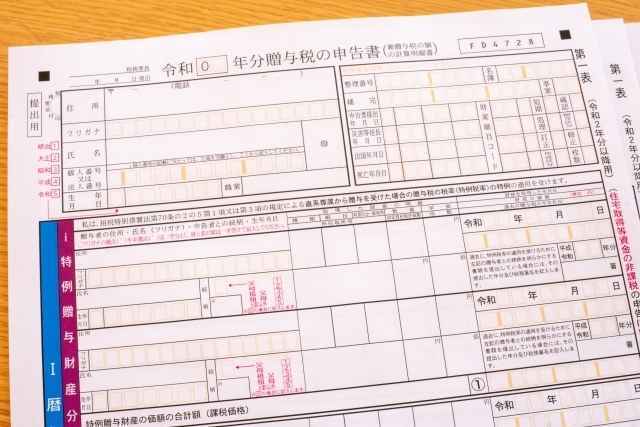
贈与税とは?
贈与税は、個人から財産をもらった際に課される税金です。国税庁によると、「個人から財産をもらったときにかかる税金」とされています。例えば、親族から現金や不動産を受け取った場合には贈与税の対象となります。
ただし、会社や法人からの贈与は一般的に所得税の対象となるため注意が必要です。また、生前に財産を受け取る「生前贈与」も贈与税の対象になります。
贈与税の課税方式
1. 暦年課税
暦年課税とは、1年間(1月1日~12月31日)の間に110万円までの贈与であれば非課税となる制度です。
例:
- AさんがBさんに200万円を贈与した場合
- 基礎控除額(110万円)を差し引いた90万円が課税対象
2. 相続時精算課税
相続時精算課税とは、累計2,500万円までの贈与が非課税となる制度です。
適用条件:
- 受贈者が18歳以上の子や孫
- 贈与者が60歳以上の親や祖父母
この制度を適用した場合、最終的に相続時にまとめて精算されます。
贈与税の税率
贈与税の税率は、「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。
1. 一般税率
一般税率は、夫婦・兄弟・親から未成年の子供などへ財産を贈与した場合に適用されます。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
2. 特例税率
特例税率は、直系尊属(父母・祖父母)からの贈与で、受贈者が20歳以上の場合に適用されます。
| 課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
贈与税の計算方法
計算例
例:800万円の贈与を受けた場合(一般税率)
- 800万円
- 110万円(基礎控除)= 690万円(課税対象額)
- 690万円の税率40%、控除額125万円
- 690万円 × 40% = 276万円
- 276万円
- 125万円 = 151万円(納税額)
生前贈与になる場合・ならない場合
贈与税がかかるケース
- 親が子の借金を肩代わりする
- 親の家を子の名義に変更する
- 保険料を支払っていない人物が満期保険金を受け取る
贈与税がかからないケース
- 生活費・教育費の支援
- 香典・見舞金・お年玉(社会通念上妥当と認められる金額)
- 法人からの贈与(所得税の対象)
贈与税を節税できる制度
1. 直系尊属からの教育資金の一括贈与
- 1,500万円まで非課税
- 30歳未満の子・孫が対象
- 金融機関を通じて管理が必要
2.直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与
- 結婚資金300万円、子育て資金1,000万円まで非課税
- 受贈者の年齢が18歳以上50歳未満
- 金融機関を通じて送金
3.直系尊属からの住宅取得等資金の贈与
- 受贈者の年齢が18歳以上
- 一定条件を満たせば最大1,000万円まで非課税
- 贈与を受ける年の所得が2,000万円以下
4. 夫婦間での居住用不動産の贈与
- 結婚20年以上の夫婦に適用
- 居住用の不動産を贈与した場合
贈与税の注意点
- 相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象
- 名義預金とみなされると相続税の対象
- 定期贈与と判断されると課税対象になる
まとめ
贈与税は110万円を超えると課税されますが、非課税制度を活用することで節税可能です。生前贈与を計画する際は、適用できる特例制度を確認し、税務署のルールに従って適切に申告しましょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。不動産ディベロッパーを中心にホテル、飲食業、製造業など幅広い事業の監査業務に従事。百貨店、その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。

 お問い合わせ
お問い合わせ
 税理士紹介の無料相談はこちら
税理士紹介の無料相談はこちら










