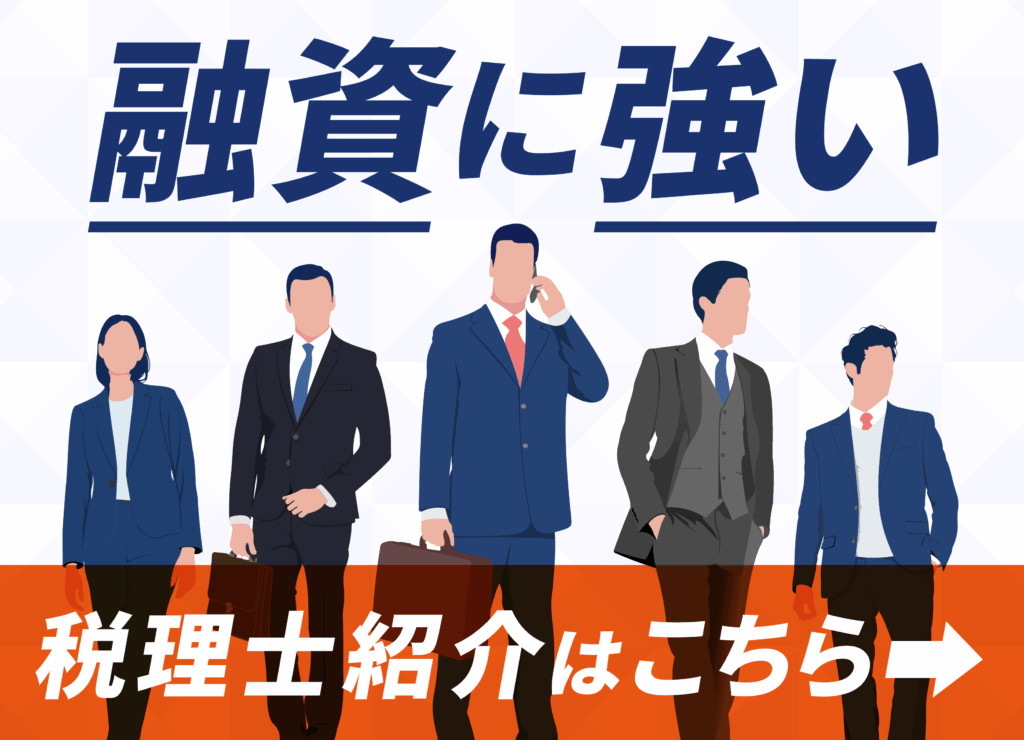年金受給者は確定申告が必要?不要?ケース別に徹底解説
年金受給者は原則確定申告が必要です。ただし、公的年金受給者でも確定申告が不要なケースもあります。この記事では確定申告が必要なケースと不要なケース、確定申告不要制度の概要、確定申告で必要な書類などについて解説していきます。

年金受給者は確定申告は必要?
年金受給者が確定申告をしないとどうなる?
このような悩みや疑問を解決していきます。
結論から言うと、年金受給者は原則確定申告が必要です。
しかし、年金受給者の中でも確定申告が不要な方がいることも事実です。
そこで、この記事では確定申告が必要なケースと不要なケース、確定申告不要制度の基本事項、確定申告で必要な書類などについて解説していきます。
年金受給者は確定申告が必要?
上記のように、年金受給者は原則確定申告は必要です。
そもそも、年金受給者とは公的年金を受給している人を指します。
公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類があり、年金受給者で確定申告が必要かどうかは、課税対象となる公的年金の受給額や公的年金以外の所得金額で決まります。
確定申告が必要なケース
年金受給者で確定申告が必要なケースは、次の通りです。
- 公的年金以外の所得が年間20万円を超える人
- 公的年金等を年間400万円以上受け取る人
参考:公的年金等の課税関係
公的年金以外の所得が年間20万円を超える人や、公的年金を年間400万円以上受け取る人は確定申告をして納税しなければいけませんので、注意してください。
確定申告が不要なケース
年金受給者で確定申告が不要なケースは、次の通りです。
- 源泉徴収の対象となる公的老齢年金の収入金額が400万円以下
- 公的年金以外の所得金額が20万円以下
参考:公的年金等の課税関係
上記に当てはまる人は、年金受給者でも確定申告は不要です。
ただし、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で確定申告が必要ない場合でも住民税の申告が必要なケースもありますので、注意してください。
詳しくは、お住いの市区町村の窓口で確認してみてください。
確定申告不要制度とは
確定申告不要制度とは、公的年金の収入金額が年400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下の場合、確定申告が不要になるという制度です。
公的年金は「雑所得」として課税の対象になっており、原則確定申告が必要です。
しかし、年金受給者の方の確定申告の手続きに伴う負担を減らすため、確定申告不要制度が設けられています。
確定申告不要制度の対象者か判断する方法
確定申告不要制度の対象となるのは、次の条件どちらにも当てはまる人です。
- 公的年金等の合計所得金額が年400万円以下で、かつその所得全てが源泉徴収の対象
- 公的年金以外の所得が20万円以下
「公的年金等の合計所得金額が年400万円以下」というのは、老齢基礎年金、厚生年金、共済年金、iDeCoの給付金など複数の年金を合算した金額で判断します。
さらに、確定申告不要制度の対象となるのは、公的年金等の収入全てが源泉徴収の対象であることが条件です。
これは、源泉徴収によりあらかじめ所得税を引いた金額を支給することで、所得税の納付が不要になるためです。
確定申告不要制度の注意点
確定申告不要制度の対象者となっていても、住民税の申告が必要な場合もあります。
例えば、公的年金等の所得のうち、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されていない控除の適用を受ける場合は、住民税の申告が必要になります。
また、公的年金以外にパートや再雇用などで給与があるケースでは確定申告が必要になりますので、注意してください。
年金受給者でも確定申告をすることで還付されるケース
確定申告不要制度の対象者で確定申告が不要な方でも、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースもあります。
払いすぎた税金がある場合、それを戻してもらうためには確定申告が必要です。
年金を受給している方でも確定申告を行うことで還付されるケースは、次の6つがあります。
- 家族構成の変化
- 医療費の支払い
- 社会保険料・生命保険料・地震保険料の支払い
- 災害または盗難にあった
- 住宅ローンを利用してマイホームの購入またはリフォームをした
- 扶養親族等申告書を提出していない
家族構成の変化
家族構成が変化した時は、確定申告をすることで払いすぎた税金が返ってくる可能性があります。
例えば、離婚や死別した人は一定の要件のもと「寡婦控除」の対象となり、27万円が控除されることがあります。
また、何らかの理由で親族を扶養することになった場合、「扶養控除」の対象となり16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下の場合は38万円、特定扶養親族である19歳以上23歳未満の場合は63万円が控除となる仕組みです。
医療費の支払い
年間の医療費が10万円を超える場合(総所得金額200万円未満の場合は総所得金額5%を超える)、医療費控除を受けられる可能性があります。
医療費控除の上限は200万円です。
20万円、または総所得金額の5%を超えた時、その超えた分が全額医療費控除の対象で税金が返ってくる仕組みです。
年金から源泉徴収税が天引きされている場合は、積極的に医療費控除を利用して払いすぎた税金を取り戻しましょう。
医療費控除を利用する際は医療費の支払い証明書として領収書を保管しておく必要があります。
社会保険料・生命保険料・地震保険料の支払い
社会保険料・生命保険料・地震保険を支払っている場合、それぞれ一定額が控除金額になります。
これは、家族分の保険料も同様です。
社会保険料を支払っている場合はその金額、生命保険料・地震保険を支払っている場合は最大で17万円の控除を受けられるので、その分所得税が還付されます。
災害または盗難にあった
災害または盗難にあった時は、雑損控除を受けられます。
雑損控除の金額は、「(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%」と「(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円」のいずれか多い方の金額です。
参考:国税庁|災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
住宅ローンを利用してマイホームの購入またはリフォームをした
住宅ローンを利用してマイホームの購入またはリフォームをした場合も、払いすぎた税金が返ってくる可能性が高いです。
マイホームを購入した時は「住宅借入金特別控除」が適用となり、その後10~13年に渡ってローン残高の0.7%分の控除を受けられます。
リフォームした場合は、「特定増改築住宅借入金等特別控除」が適用となり、その後10年に渡ってローン残高の0.7%の控除を受けられます。
扶養親族等申告書を提出していない
扶養親族等申告書を提出していない場合も、払いすぎた税金が返ってくる可能性があります。
公的年金等の受給者で源泉徴収の対象となる人には、「扶養親族等申告書」が届きます。
扶養親族等申告書は、年金から源泉徴収される所得税に対し、配偶者控除などの各種控除を受けるために必要な書類です。
扶養親族等申告書を提出していない場合でも、確定申告をすることで払いすぎた税金が返ってきます。
確定申告で必要な書類
確定申告をする際は、さまざまな書類が必要です。
その中には、申告者全員が必要な書類と収入・所得控除に関する書類に分けられます。
申告者全員が必要な書類
年金受給に限らず、申告者全員に必要な書類は、次の4つです。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
- 確定申告書(「第一表」と「第二表」)
- 利用者識別番号(e-Taxで電子申告をするために必要な個人の識別番号)
- 銀行口座が分かるもの(通帳キャッシュカードなど)
これらの書類は必ず必要になります。
収入に関する書類
収入に関する書類で必要なものは、以下の2点です。
- 収支内訳書
- 源泉徴収票
源泉徴収票は2019年分の申告から添付と保存が不要になりましたが、適切に保管しておくことをおすすめします。
なぜなら、住宅ローンやリフォームをする際など、所得の証明として源泉徴収票の提出が求められる場合が多いからです。
また、青色申告をする人は、上記2点とは別に「青色申告決算書」を提出する必要があります。
所得控除に関する書類
所得控除を受ける際は、所得控除に応じて必要な書類を準備する必要があります。
- 医療費控除:医療費の明細書・領収書
- 社会保険料控除:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社が発行する控除証明書
- 寄附金控除:寄付金受領証明書
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済等掛金払込証明書
年金受給者でも確定申告が必要か確認しよう
この記事では確定申告が必要なケースと不要なケース、確定申告不要制度の概要、確定申告で必要な書類などについて解説してきました。
年金受給者は原則確定申告が必要ですが、不要なケースもあります。
ただし、確定申告をする必要がない人でも、確定申告をすることで納めすぎた税金が返ってくる可能性があります。
各種控除を受けるためには確定申告が必要です。
確定申告をし忘れていたり、控除漏れがないように、忘れずに確定申告をしておきましょう。

【監修者】代官山税理士法人 / 代表 大勝 健司
会計士試験合格後、監査法人に入社。幅広い事業の監査業務に従事。 その後、売上高数千億の一部上場企業(小売業)にて、企業内会計士として経理業務に従事。税理士として、決算書の作成、法人税申告書、相続税の相談から申告実務全般にも携わる。また社会保険労務士として事業会社において各保険の入退社手続き、役員及び従業員向けの退職金制度導入、就業規則の作成等に至るまでの労務を経験。社会保険の知識にも明るい。ヒトとカネの融合的視点からのアドバイスを可能とする。
みんなの税理士相談所は最適な税理士をご紹介
- 忙しくて決算・確定申告に手を回せていない
- 自分では出来ない節税対策を依頼したい
- 要望に合った顧問税理士を探したい
みんなの税理士相談所では、このようなお悩みや要望をお持ちの方に税理士を検索できるサービスの提供と、税理士の紹介をしております。
税金まわりのお悩みや要望は、数多くあり、ネットで調べて解決するには難しいと感じた方もいるでしょう。当サービスでは、相談内容やお住まいの地域ごとに最適な税理士に出会うことが可能です。
以下のお問い合わせフォームから具体的な内容を入力できるので、お気軽にご利用下さい。

 お問い合わせ
お問い合わせ
 税理士紹介の無料相談はこちら
税理士紹介の無料相談はこちら